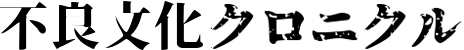昭和20年、日本は敗戦を迎えた。空襲で焼け野原となった都市部には「闇市」が立ち並び、既存の価値観や道徳は音を立てて崩れ去っていた。そんな混沌とした時代、大人たちの作ったルールを嘲笑うかのように、暴力と腕っぷしだけでのし上がろうとした若者たちがいた。それが「愚連隊(ぐれんたい)」である。
彼らは単なる不良少年ではない。かといって、任侠道を重んじる博徒やテキヤといった伝統的なヤクザとも異なる。組織の論理よりも個の欲望を優先し、刹那的な暴力を振るう彼らは、戦後復興期の闇社会において最も危険で、予測不能な存在として恐れられた。本記事では、昭和の闇に強烈な爪痕を残した愚連隊の実態と、その特異な生態について解説していく。
秩序なき焼け跡で生まれた「愚連隊」という生き方
「愚連隊」という言葉の語源は、予期せぬ言動をする、道から外れるという意味の「ぐれる」に、集団を表す「連隊」を合わせたものだと言われている。その原型は戦前から存在したが(モガ・モボの時代の不良など)、彼らが爆発的に勢力を拡大したのは、やはり戦後の混乱期においてである。
復員兵や特攻隊の生き残り、あるいは空襲で親を亡くした戦災孤児たち。行き場を失った若者たちは、生きるために徒党を組み、繁華街の闇市を縄張りとして活動を始めた。新宿、渋谷、銀座、浅草。彼らは飲食店からの用心棒代(みかじめ料)の徴収や、物資の横流し、ヒロポン売買、あるいは敵対グループとの抗争に明け暮れた。
当時の警察力は弱体化しており、治安は崩壊寸前だった。そんな無法地帯において、頼れるのは己の拳と仲間だけ。愚連隊は、社会への不満と行き場のないエネルギーを暴力という形で発散させる、時代の歪みが生んだ「徒花(あだばな)」だったのである。
仁義なき凶暴性。ヤクザとは一線を画す「スタイル」
愚連隊を語る上で欠かせないのが、既存のヤクザ組織との決定的な違いである。
伝統的なヤクザ(博徒・テキヤ)には、親分・子分の契りを交わす「盃(さかずき)」の儀式があり、家父長制的なヒエラルキーと厳格な掟(任侠道)が存在した。「素人には手を出さない」「着物を着てドスを持つ」といった古い美学が、ある種の抑止力として機能していた側面もある。
しかし、愚連隊にはそれが通用しなかった。彼らの多くは盃を交わさず、あくまで兄弟分や遊び仲間というフラットな関係性で結びついていた。それゆえに統制が効きにくく、一度暴れだすと手がつけられない。
ファッションも特徴的だった。彼らは着物ではなく、進駐軍の影響を受けたアロハシャツや開襟シャツを好み、リーゼントやオールバックの髪型でサングラスをかけるなど、アメリカナイズされたスタイルをいち早く取り入れていた。武器もドスにこだわらず、ジャックナイフや拳銃(ポンプ)を躊躇なく使用する。古いヤクザからは「チンピラ」と蔑まれたが、その近代的な武装と無慈悲な暴力は、旧来の組織を圧倒するほどの脅威となっていった。
伝説となった「安藤組」と暴力団への吸収
中でも異彩を放ったのが、元特攻隊員であり大学生でもあった安藤昇率いる「安藤組」である。渋谷を拠点に、組員には大学生を多く抱えるなど知的な側面を持ちながら、その実態は極めて凶暴。「インテリヤクザ」の先駆けとして、戦後アウトロー史に独自の伝説を刻んでいる。
しかし昭和30年代後半に入ると、国家による治安維持活動が本格化する。警察による大規模な暴力団取り締まり、いわゆる「頂上作戦」が展開される中、無軌道な活動を続けていた愚連隊もまた、厳しい弾圧の対象となった。
法の網が狭まる中、多くの愚連隊は「解散」か「傘下入り」かの選択を迫られる。結果として、多くの有力な愚連隊は、山口組などの巨大広域暴力団に吸収されていった。例えば、後に「殺しの軍団」として恐れられた柳川組も、元々は大阪の愚連隊からスタートしている。彼らはその武闘派としての実力を買われ、組織の切り込み隊長としてのし上がっていったのだ。
こうして、街角から純粋な意味での「愚連隊」は消滅した。しかし、彼らが持っていた「組織に縛られない自由なスタイル」や「既得権益への反発心」は、後の暴走族カルチャーや、現代の半グレ集団にも通じる部分があるかもしれない。焼け跡の闇を駆け抜けた彼らの無軌道な青春は、昭和という激動の時代を象徴する、暗く激しい輝きを放ち続けている。